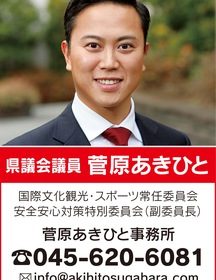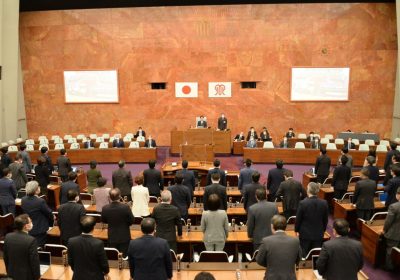令和7年第2回定例会 本会議 代表質問

5月15日から7月25日まで開催された令和7年第2回定例本会議にて重要な答弁を数々引き出し、次々に提案させていただきました。ご報告させていただきます。
令和7年6月18日(水)本会議 代表質問
(質問要旨)
1 県民の安全・安心につながる取組について
(1) ヘイトスピーチやインターネット上の誹謗中傷などの人権課題への対応について
県は、かながわ人権施策推進指針により、人権がすべての人に保障される地域社会を目指しているが、そのためには、こうした意識啓発を含め、人権課題への対応を強化すべきと考える。
そこで、ヘイトスピーチやインターネット上の誹謗中傷などの人権課題に対して、県は今後どのように取り組んでいくのか、所見を伺う。
(知事答弁)
県民の安全・安心につながる取組について何点かお尋ねがありました。まず、ヘイトスピーチやインターネット上の誹謗中傷などの人権課題への対応についてです。現在県では、独自にインターネット上のヘイトスピーチ等のモニタリングを実施しており、問題のある投稿について、昨年3月からは直接プロバイダへ削除を依頼し、迅速な被害防止に努めています。しかし、こうした投稿は後を絶たず、誹謗中傷を防止していくためには、一人ひとりが人権課題を正しく理解し、お互いを尊重して、多様な個性を認め合う意識の醸成が重要です。そこで県は、昨年度、主に小学生から高校生までの若年層に人権の大切さを伝えるポータルサイトを開設し、直接相手が見えないSNSで、加害者にも被害者にもならないための心がけをまとめた動画やマンガを掲載しています。
また、駅やバス車内のデジタルサイネージなども活用して、幅広い年齢層への周知にも取り組みます。さらに、今年度、本県としては初の取組となる人権意識調査を実施します。この調査により、今、県民の皆様が感じている人権課題や県に求める取組などを把握し、差別や偏見により、生きづらさを感じている当事者のご意見も伺いながら、人権課題への対応強化に向けて取り組んでまいります。
(再質問)
1点、再質問をさせていただきます。
「ヘイトスピーチやインターネット上の誹謗中傷などの人権課題への対応について」であります。答弁の中で、今年度人権意識調査を行うとのことでありますけれども、できるだけ幅広く県民にアプローチすることが望ましいと考えていますが、どのような方法で調査を行うのか、知事の所見を伺います。
(答弁)
それでは、再質問にお答えします。人権意識調査の実施方法についてのお尋ねでありました。意識調査は、民間調査会社に委託をして、県内在住の18歳以上の方を対象に、インターネットにより実施します。調査にあたっては、回答者の偏りが出ないよう、調査に協力いただくモニターを、性別や年代別に6区分に分け、500人ずつ、計3,000人に回答してもらう予定です。この調査により、県民の皆様の声をしっかりと受け止め効果的な施策につなげてまいります。答弁は以上です。
(要望)
知事から再度の答弁をいただきました。要望をさせていただきたいと思います。
ヘイトスピーチやインターネット上の誹謗中傷などの人権課題ですけれども、知事より今「県民への人権の意識調査」を行う旨の答弁がありまして、その調査結果を踏まえた上での人権施策指針の充実を図る旨答弁いただいたと認識しております。ヘイトスピーチやインターネット上の誹謗中傷などの人権課題は、SNSやAIの発展により深刻化していくことが懸念されます。調査結果を踏まえた上で、より踏み込んだ、実効性のある対応を求めたいと思います。また、ネット上の県からの直接の削除依頼についてもAIなどを活用し、より件数を増やし人権救済につなげていただく取組を求めます。
(質問要旨)
1 県民の安全・安心につながる取組について
(2) ストーカー被害者等に対する相談支援の取組について
ストーカーや暴力被害を受けた方の心身の安全を守るための支援に関する情報が、支援を必要とされる方に、未だ十分に届いていないのではないかと懸念する。いくら良い支援策があっても、そのこと自体が知られていなければ、実際の活用につながらない。現在もストーカーやDV被害に悩んでいる女性の安全を守るためには、早急に相談窓口を含めた支援の仕組みについて、広く知っていただき、利用してもらえるように、女性相談支援の認知度を高める必要があるのではないか。そこで、ストーカー被害を含めた様々な困難な問題を抱える女性に対する、相談支援など施策の普及啓発に県としてどのように取り組んでいくのか、所見を伺う。
(知事答弁)
次に、ストーカー被害者等に対する相談支援の取組についてです。
困難を抱える女性の相談支援を担う県として、今回、川崎で起きた事件を大変重く受け止めています。これまで県は、ストーカーやDVなど困難を抱える女性のための相談窓口を設け、ホームページやリーフレット等により、周知に努めてきました。特に、支援につながりにくい若者に向けて、マンガを使った相談窓口の周知カードを作成し高校や大学、インターネットカフェなどで配布してきました。さらに先日、緊急シンポジウムを開催し、事件を受け不安を感じる方々に対して、相談窓口や一時保護の仕組みについてお伝えしました。シンポジウムの参加者からは、「今日初めて相談窓口を知った」との声もあり、ストーカーやDV被害に悩む方々へ必要な支援を届けるには、もっと当事者の状況を踏まえた普及啓発の工夫が必要です。そこで、今後は、若年層や、困りごとを抱えた方などをターゲットとして情報を届けることができる、SNS広告などの充実を図るほか、民間団体や関係機関と連携して効果的な情報提供に取り組みます。また、警察に相談に来た被害者が、行政の支援にもつながりやすくなるよう、警察署や交番にも相談窓口の周知カードを配布するなど、被害者の目線に立ち、普及啓発にしっかりと取り組んでまいります。
(要望)
次に、「ストーカー被害者等に対する相談支援の取組について」であります。ストーカー等の被害を受けられている方を救済するために「ワンストップ」で被害救済を求められる窓口の設置が急務です。その窓口があることの周知・啓発をより情報が被害を受けられた方に届けられるかが重要だと思います。県当局の他部署との連携にとどまらず、市町村や女性相談支援を行っているNPO法人などの民間団体とも連携を密にしながら、ストーカー等の被害を受けている方を全員救済するという強い決意を持って取り組んでいただくことを求めます。
(質問要旨)
1 県民の安全・安心につながる取組について
(3) 女性の視点に立った避難対策について
本県でも、平成9年3月に策定した「避難所マニュアル策定指針」の改訂を重ね、市町村とともに、性別等に配慮した避難所運営や避難者の生活環境の向上に取り組んでいると承知しているが、地域によっては、未だに、男性中心の視点からなかなか脱却できていない面が、見受けられるという声を耳にする。これまでの災害から学んだ教訓を生かし、誰もが平等に避難所生活を送ることが出来るよう、特に平時から女性等の視点を踏まえた避難対策にしっかりと取り組み、自主防災組織や避難所運営に携わる地域の方々に対して、一層の周知・啓発を図っていく必要があると思う。そこで、避難者の生活環境の向上に向けて、特に、女性の視点に立った避難所運営に取り組んでいくべきと考えるが、今後県はどのように取り組んでいくのか、所見を伺う。
(知事答弁)
次に、女性の視点に立った避難対策についてです。
県では、東日本大震災以降、女性の避難所運営の参画や、女性に配慮した物資の備蓄など、女性の視点を踏まえた対応を避難所運営マニュアル策定指針に反映してきました。また昨年度は、県や市町村の職員を対象に、女性の有識者や県の防災アドバイザーの国崎信江さんを講師に迎え、女性の視点を踏まえた避難所運営や、周産期の女性の避難をテーマとした講習会を開催しました。さらに県は、今年3月に公表した地震被害想定調査の中で、様々な立場の県民の目線から被害の状況を描く県民シナリオを作成しています。その中で、例えば、避難所において男性が生理用品を配布しているといった具体的な場面を設定し、本来は、女性に配慮して、女性が配るべきであるとして、正しい対応策を提示しました。これを基に、避難所運営に女性の視点が反映され、避難生活の改善につながるような動画を今年度中に作成し、かながわ防災パーソナルサポートで発信するなど、普及啓発の強化に取り組みます。また、県民の皆様が避難生活での対応や事前の備えなどを学べる、防災知識を一つにまとめた啓発冊子を新たに作成し、妊産婦を優先した救援物資の受取りやプライバシーの確保といった避難所における女性への配慮のポイントなどを盛り込みたいと考えています。県は、こうした様々な取組を通じて、女性の視点に立った避難所運営のさらなる改善に努めてまいります。
(要望)
次に、女性の視点に立った避難対策についてである。昨年度、県は、能登半島地震などの教訓をもとに、プライバシーを確保するための避難所用テントなどの整備を行ったことは承知している。避難生活の環境改善のためには、こうしたハード面の整備はもちろん重要だが、女性が少しでも快適に避難生活を過ごしていくためには、女性の視点に立ったソフト面での対策が欠かせない。県は、更なる普及啓発などを通じて、避難所を設置・運営する市町村をしっかりと後押しすることを求める。
(質問要旨)
1 県民の安全・安心につながる取組について
(4) 富士山火山対策について
万が一、富士山が大噴火を起こした際には、溶岩流に加え、広範囲にわたる火山灰の影響で、道路や鉄道、航空機などの交通網、電気の供給や通信環境、上下水道などライフラインや住民の生活に深刻な影響を及ぼすことも大いに危惧される。こうした中、国は今年の3月に「首都圏における広域降灰対策ガイドライン」を公表し、大規模噴火が発生した場合の広域降灰対策にかかる考え方や留意点等を取りまとめた。本県においても、国のガイドラインを踏まえながら、関係団体や有識者などと連携して、降灰の影響も含め、幅広く対策の検討・調整を進めていく必要があるのではないかと考える。そこで、本県に深刻な影響を及ぼす可能性のある降灰への対応を含め、富士山火山対策の更なる充実に取り組むべきと考えるが、県は今後どのように取り組むのか、所見を伺う。
(知事答弁)
次に、富士山火山対策についてです。令和3年に公表された富士山ハザードマップでは、富士山が大規模噴火した場合、溶岩流が本県の7市町に到達する可能性が示されました。一方、降灰については、当時、国が対処の考え方を整理中であったことから、県はまず、溶岩流を対象に市町村域を越える広域避難の考え方や手順を整理した富士山火山広域避難指針を令和4年度に策定し、市町村と共有してきました。こうした中、今年3月、国は富士山噴火時の首都圏における広域降灰対策として、住民はできる限り自宅にとどまり生活を継続すること、木造家屋の倒壊の危険がある降灰量30㎝以上の地域は原則避難とするガイドラインを公表しました。そこで県は、このガイドラインを踏まえ、在宅避難を想定した備蓄のあり方や降灰量に応じた広域避難の考え方、その手法などを、市町村とともに検討し、今年度中に県の指針に反映したいと考えています。また、大量の火山灰に備え、再利用や埋め立て、海洋投入などの最終処分の調整や県域をまたぐ広域避難など、県単独では解決できない課題もあるため、国に対して、技術的・財政的支援を要望していきます。県は、今後、近隣県や市町村などと連携し、万一の大規模噴火に伴う降灰への対応を含め、富士山火山対策のさらなる充実に努めてまいります。
1 県民の安全・安心につながる取組について
(5) 土石流対策について
近年の集中的に大量に降る雨の状況を考えると、土石流対策は、県として取り組んでいかなければならない重要な対策であり、現在、県が進めている土石流を止めるための砂防堰堤の整備を、より一層推進していくべきと考える。そこで、土石流対策について、今後、どのように取り組んでいくのか、所見を伺う。
次に、土石流対策についてです。
土石流は、豪雨等により、土砂などと水が一体となって猛スピードで渓流を流れ、一瞬にして人命や家屋などを襲い、甚大な被害を及ぼすことから、上流部で土石流を食い止める砂防堰堤の整備は大変重要です。本県においては、昭和47年の「山北災害」以降、土石流による人的被害は発生しておらず、県がこれまで244にのぼる渓流で砂防堰堤を整備してきた効果は、着実に現れてきています。一方、砂防堰堤の整備は、大型機械の搬入や作業場所の確保が困難な、山奥での作業となり、多くの費用と時間が必要なこともあって、現在の整備率は、約3割の状況です。近年は、集中豪雨による災害が激甚化、頻発化し、令和元年の東日本台風では、土石流により、道路や鉄道などの重要なインフラに甚大な被害が発生するなど、更なる整備が必要です。そこで県は、土石流対策を「神奈川県水防災戦略」に位置付け、東日本台風が発生した令和元年度に比べ、整備予算を約1.5倍に引き上げています。また、引き続き、次期水防災戦略においても土石流対策を位置付け、重要なインフラがある緊急性が高い箇所から優先的に、砂防堰堤の整備を行います。県は、土石流から県民の、いのちと財産を守り、地域の社会・経済活動を支えるため、土石流対策にしっかりと取り組んでまいります。
(質問要旨)
1 県民の安全・安心につながる取組について
(6) 外国人犯罪に対する取組について
外国人犯罪は、単に取締りを強化するだけでなく、犯罪抑止や共生社会の実現に向けた環境整備も不可欠である。外国人が社会に円滑に適応し、日本人とともに支え合う共生社会を構築するためには、外国人に対する過度な偏見や誤解を避け、公平かつ効果的な治安維持を進めることが重要である。外国人自身が日本の法律を理解し、犯罪の加害者や被害者にならないようにするための教育や多言語に対応した情報提供を充実させることも求められている。そこで、全国及び神奈川県における外国人犯罪の検挙状況や外国人犯罪の特性を踏まえ、県警察の取組について、所見を伺う。
(警察本部長答弁)
○ 外国人犯罪に対する取組についてお答えします。
〇 はじめに、県内における外国人犯罪の検挙件数につきましては、令和5年が1,515件、令和6年が1,765件となっており、全国の場合と同様、2年連続で増加しております。
〇 外国人による犯罪の特徴として、出身国や地域別に組織化されているものがある一方、犯罪ごとに様々な国籍の構成員が離合集散を繰り返すなど、組織の多国籍化もみられます。
○ このほか、一部の外国人犯罪組織にあっては、面識のない者同士がSNS等を通じて連絡を取り合い、役割を分担しながら犯行に及ぶものもみられます。
〇 県警察では、外国人らによって組織的に敢行される犯罪に対し、関係する都道府県警察とも密接に連携しながら、重点的な取締りを推進してまいります。
〇 また、外国人が、言語や生活習慣の相違等から生ずる犯罪やトラブルに巻き込まれることがないよう、多言語を用いて作成した注意喚起のチラシを配布するなどの防犯対策や交通安全対策を行っておりますが、引き続き、関係機関・団体とも連携しつつ、こうした広報啓発活動に取り組んでまいります。以上でございます。
(質問要旨)
2 豊かな暮らしの実現について
(1) 水源環境保全・再生施策について
県民に必要なかつ上質な水の安定的確保を目的とした水源環境保全・再生施策は、重要なものと考えますが、昨今の物価上昇による県民生活への影響を鑑みると、県民負担に配慮し、超過課税の活用は必要最小限にすべきと考えます。また、超過課税を活用して水源環境の保全・再生の取組を進めていくうえでは、今後20年間で、何を目指し、どういった状態になるまで施策や超過課税を続けていくのかという明確な目標を設定していくことが、県民に理解を求める上でも必要であると考えます。そこで、知事に伺います。水源環境保全・再生施策は、次の計画期間である20年間で、目的を達成できるのか、目標設定を含めた県の所見を伺う。また、次期計画における財源措置はどのように考えているのか、超過課税による納税者一人当たりの負担額も併せて伺います。
(答弁要旨)
豊かな暮らしの実現について、何点かお尋ねがありました。まず、水源環境保全・再生施策についてです。県としては、良質な水の安定的確保という目的を掲げて、次の20年間の計画の素案を策定しました。そして、目的を達成するためには、森林関係では、県が整備して所有者に返還した森林等が、特別な手を入れなくても健全性を保てる状態になり、水源かん養等の公益的機能が持続的に発揮される必要があります。また、水関係では、生活排水処理率が向上し、河川の水質が、環境基準を下回る数値で安定的に推移していく必要があります。県としては、今後20年間で目標を達成できるよう、施策の評価と見直しを行いながら、効果的な対策に取り組んでいきますが、実際に現れる効果については、自然条件等により大きく左右されます。このため、正確な予測は難しく、現時点で目的を達成する時期の特定は困難と考えていますが、9月に策定する5か年の実行計画の素案の中で、具体的な数値目標を設定し、事業に取り組んでいきます。次に、次期計画における財源措置についてですが、現時点の想定事業費53.3億円に、現行と同規模の一般財源13億円程度を充当し、その不足額に超過課税を活用したいと考えています。
これを前提にしますと、納税者一人当たりの平均負担額は880円から820円程度に下がる見込みです。
(要望)
水源環境保全・再生施策についてであります。県民に超過課税をお願いする以上、費用対効果、適正な負担割合などについて、説明責任を果たしていくことが重要です。一般財源と超過課税それぞれによる適正な事業規模について、県内市町村と協議を重ねながら、都市部を含めたすべての県民に理解が得られるような説明を行っていただくことを求めます。また、どこまで実現すれば超過課税の徴収が終わりになるのか、ゴールを設定した上で、そのゴールに到達するには何がどれだけ必要なのかという綿密な計画や取組を求めます。
(質問要旨)
2 豊かな暮らしの実現について
(2) 経済情勢を踏まえた中小企業支援等について
物価高騰の問題に加え、第二次トランプ政権による米国の関税措置が及ぼす県内中小企業への影響が強く懸念される。さらに、先月半ばには、本県が創業地である日産自動車が、巨額の赤字を背景として、2027年度までに2万人の人員削減や世界17工場のうち7工場の閉鎖を行うとの経営再建計画を発表し、県内関連企業への影響は避けられないものと考える。これらの諸課題に直面する中小企業への支援が強く求められるが、中小企業を支援するということは、そこで働く多くの県民の雇用を守るということであり、県民の暮らしを守る意味でも県内の中小企業をしっかりと支えていくことが重要である。そこで、物価高騰や米国による関税措置、さらには日産自動車の経営再建計画を踏まえ、県内の中小企業やその従業員をどのように支援していくのか、所見を伺う。
(知事答弁)
次に、経済情勢を踏まえた中小企業支援等についてです。県ではこれまで、中小企業に対する物価高騰への対策として、資金繰り支援のほか、燃料価格高騰の影響を強く受ける貨物運送事業者や特別高圧を受電する事業者への支援などを行ってきました。また、米国による関税措置への対応としては、中小企業向けの特別相談窓口を設置するとともに、新たに、関税措置により影響を受けた中小企業を、特別融資制度の対象に追加しました。これに加え、日産自動車が5月に発表した経営再建計画も踏まえ、今月11日に、国、県、市町村と関係機関が参加する「米国関税及び日産自動車/生産縮小に関する対策協議会」を設立しました。今後、この協議会では、ワーキンググループを設置し、中小企業への影響の把握やそれに基づく効果的な施策の検討などを行っていきます。また、中小企業は県内雇用の7割以上を占めていることから、雇用面での支援も大変重要です。そこで、雇用への影響が見込まれる場合には、迅速な対応が図れるよう、神奈川労働局等との連携を強化していきます。このように、先行きが不透明な経済情勢の中、国や市町村、関係機関等と連携を図り「オール神奈川」で県内中小企業をしっかりと支援してまいります。
(質問要旨)
2 豊かな暮らしの実現について
(3) 神奈川県中小企業・小規模企業活性化推進計画の改定について
現行の計画期間であるこの7年の間には、世界的には新型コロナウイルス感染症のパンデミックや国際紛争が生じている。また、国内では、物価高騰や深刻な人手不足、加えて最近では米国関税措置の問題などが発生しており、中小企業をとりまく環境は大変厳しくなっている。社会経済情勢が目まぐるしいスピードで変化している昨今において、中小企業がこうした問題を乗り越え、今後も成長していくためには、計画改定にあたっても環境の変化に柔軟に対応する必要があるのではないか。そこで、多くの課題を抱える中小企業に対し、今後も成長を促し、持続的な県内経済の発展を目指すため、中小企業・小規模企業活性化推進計画の改定に向けて、どのように取り組んでいくのか、所見を伺う。
(知事答弁)
次に、神奈川県中小企業・小規模企業活性化推進計画の改定についてです。現行の第4期計画は、今年度で7年間の計画期間が満了することから、この間の社会経済情勢の変化等を踏まえた改定を行う必要があります。先月開催した中小企業・小規模企業活性化審議会では、次の計画に向けて、現行計画の振返りを行うとともに、今後の取組の方向性や目指す姿について議論を行ったところです。審議会では、「人手不足が目下の最大の課題である」、「現行計画期間7年は、先を見通すには長過ぎる」などの意見がありました。そこで次期計画では、現行計画策定後に顕在化した、人手不足や価格転嫁、賃上げ等の経営課題に対し、生産性の向上やAI等も含めたDXの推進などにより、積極的に取り組んでいきたいと考えています。こうした取組により、変化に対応した県内産業の活性化と多様な人材の活躍促進を図り、労働力不足社会におけるさらなる経済成長の実現を目指します。また、計画期間についても、昨今の変化が激しい社会経済情勢を受け、より短い期間にしたいと考えています。計画改定に当たっては、今後、審議会や議会、支援機関、県民の皆様からも広くご意見をいただきながら、より実効性のある計画となるように策定してまいります。
(再質問)
神奈川県中小企業・小規模企業活性推進計画の改定についてであります。改定後の計画における取組期間について、知事からも、短い期間にしたいというご答弁がありました。現行の7年間よりも短くなるということだと考えておりますけれども、改定後の計画期間について、現時点で具体的にどのように考えているのか。知事の所見を伺います。
(知事答弁)
改定後の計画期間についてのお尋ねがありました。新型コロナウイルス感染症や能登半島地震、米国関税措置など、昨今の社会の変化は目まぐるしく、経済状況等の先行きは非常に不透明です。
そこで、現時点では計画期間を5年間とし、さらに、不測の変化にも対応することができるよう、計画期間の折り返しの年度に当たる3年目に、中間見直しを行う方向で検討を進めてまいります。
(要望)
昨今の目まぐるしい変化をする社会情勢の中で、想定外の課題というものが出てくると思います。柔軟に対応できる期間、そして組織体制の構築、計画の見直しへの対応を引き続きお願いしたいと思います。
(質問要旨)
2 豊かな暮らしの実現について
(4)神奈川県スポーツ推進計画の改定について
国においては、スポーツ基本法が改正された。スポーツ基本法は、スポーツの推進のための基本的な法律として、議員立法により平成23年に制定されたものである。このスポーツ基本法の改正案が、今月、国会に提出され、6月13日に成立し、制定から14年が経過した中での大幅な改正がなされたと伺っている。神奈川県スポーツ推進計画は、スポーツ基本法に基づく地域スポーツ推進計画としても位置付けられていることから、県としても今後新たな対応が必要になってくると考える。そこで、神奈川県スポーツ推進計画の改定について、スポーツ基本法の改正の動きを踏まえ、どのような考え方で進めていこうとしているのか、所見を伺う。
(知事答弁)
次に、神奈川県スポーツ推進計画の改定についてです。県では、現行計画に、生涯スポーツ社会の実現や、スポーツの持つ力による地域活性化、共生社会の実現などを掲げ、施策を展開してきました。そして、今年度が現行計画の最終年度になるため、現在、計画改定の準備を進めています。今年3月のスポーツ推進審議会では、誰もがスポーツに親しめる環境づくりや、スポーツを通じた共生社会の実現に向けた取組の一層の充実などを盛り込んだ改定骨子案をお示しし、ご議論いただきました。こうした中、先般、スポーツ基本法が改正されました。背景には、スポーツ基本法が制定されてから、14年が経過し、社会環境が大きく変化する中、健康長寿社会の実現や人との豊かなつながりなど、スポーツを通じた社会課題の解決に期待が高まっているという状況があります。改正内容には、そうした状況を踏まえ、スポーツによる地域振興や共生社会の実現など、既に、本県が取り組んでいる項目のほか、国や自治体の新たな責務として、スポーツ選手に対する暴力やSNSによる誹謗中傷の防止なども盛り込まれています。そこで、計画改定に向けては、法の改正内容をしっかりと踏まえて、検討を進めてまいります。
答弁は以上です。
(質問要旨)
3 県政の諸課題について
(1) 厳しい安全保障環境を踏まえた基地負担軽減に向けた取組等について
我が国をとりまく状況は、安全保障環境の変化、そして、トランプ政権の発足といった非常に難しい局面にある。そのような中においても、知事にはリーダーシップを発揮し、基地負担軽減に向けて国へ強く働きかけるとともに、県自ら情報収集を行い、基地負担軽減に向けた施策に結び付けていただきたい。そこで、①厳しい安全保障環境を踏まえ、基地負担軽減に向けた取組をどのように進めるのか、また、②米政権の動向等に関する情報収集についてどのように考えるのか、所見を伺う。
(知事答弁)
県政の諸課題について何点かお尋ねがありました。まず、厳しい安全保障環境を踏まえた基地負担軽減に向けた取組等についてです。本県には、都市部に多くの米軍基地が所在し、多大な基地負担が生じていることから、安全保障環境が厳しい中でも、負担軽減に取り組むことが重要です。このため、私が会長を務める渉外知事会や県市連絡協議会等を通じ、基地の返還や日米地位協定の改定、騒音問題の解決等を国に求めており、今後も、基地負担軽減を国に働きかけていきます。次に、米政権の動向等に関する情報収集についてですが、基地問題を解決し、基地負担を軽減するためには、在日米軍の活動や、その背景にある米国の政策等に関する情報収集等が重要であると認識しています。特に、現トランプ政権は、経済政策などの重要政策について、米国の従来の方針を大きく変更しており、安全保障政策の動向についても、情報の収集・分析を強化する必要があると考えます。具体的には、米国政府の公表文書等を積極的に収集するとともに、専門機関や専門家の知見も活用し、米政権の動向等の総合的な分析を行っていきます。今のところ、米国が日米安全保障体制に関わる政策を大きく変更するとの情報はありませんが、今後、基地問題に影響する政策の変更等が明らかになった場合には、国に対し、具体的な影響について情報提供を求めるとともに、基地周辺への影響を最小限にするよう働きかけてまいります。
(要望)
まず、「厳しい安全保障環境を踏まえた基地負担軽減に向けた取り組み等について」であります。日米同盟は日本の安全保障にとってまさに基軸であります。しかし、多数の米軍基地を有する本県にとって、基地負担軽減はしっかりと取り組むべき重要事項であると考えております。先が読みにくい世界情勢ではありますが、米政権の動向等に関し、より積極的な情報収集に取り組むことにより、世界情勢を把握し適時適切な働きかけを通じて、県民のための基地負担軽減に取り組むことを求めます。
(質問要旨)
3 県政の諸課題について
(2)県立高校に期日前投票所を設置することについて
高校における期日前投票所の設置状況について他県の状況を調査してみると、青森県では令和3年の衆議院選挙で9か所、令和4年の参議院選挙では秋田県では3か所、長野県では6か所、茨城県では13か所となっているが、神奈川県、東京都、埼玉県は残念ながら実績がない。そこで、若年層の投票率の向上及び主権者教育の観点からも他県ですでに実績がある県立高校への期日前投票所の設置を進めるべきと考えるが、現在の取組状況と今後の展開について、所見を伺う。
(選挙管理委員会書記長答弁)
選挙管理委員会関係の御質問にお答えします。県立高校に期日前投票所を設置することについて、お尋ねがありました。これまで本県では、大学に期日前投票所が設置された事例はありましたが、高校については、選挙権を持つ18歳に達している生徒の数が少ないことや、有権者にとって、より利便性の高い場所への設置が優先されたため、設置事例はありませんでした。しかしながら、県立高校への期日前投票所の設置は、選挙権の有無に関わらず、高校生への選挙啓発としても意義があると考えられます。そこで、県選挙管理委員会では、県教育委員会と協定を締結し、今年の参議院議員通常選挙における県立高校への期日前投票所の設置に向け、設置を希望する市町村選挙管理委員会を地元の県立高校に紹介するなど、実現に向けた調整を行いました。その結果、県内で初めて、伊勢原市にある県立伊志田高校において、生徒や地域住民を対象とした投票所が設置されることとなり、現在、さらにもう1校においても、設置に向けて準備が進められています。県選挙管理委員会としては、今回の取組について、市町村選挙管理委員会や県教育委員会と、その成果や課題等を検証した上で、他の県立高校にさらに展開できるよう、検討を進めてまいります。答弁は以上です。
(要望)
県立高校に期日前投票所を設置することを通じて、主権者教育の充実は非常に重要だと考えています。加えて、伊志田高校でも、地域住民の方が使えるということでありましたけど、様々な理由から投票所に行くことが困難になる方もいらっしゃいます。高校生だけではなく、可能な限り地域の住民にも開放することで、多様なニーズに対応していくことができると考えています。そして、そのことにより投票率の向上を図っていくことで、県の民主主義の充実を図っていくことができると思いますので、求めたいと思います。また、期日前投票所の設置について、県の教育委員会と市町村とも連携しながら、水平展開により取組を広げていくことを求めます。
(質問要旨)
3 県政の諸課題について
(3)障害者支援施設や障害者グループホームの待機者について
県は、令和6年12月、県内の障害者支援施設や障害者グループホームの利用を希望する人たちの調査を実施したと承知している。令和5年4月に施行した「当事者目線の障害福祉推進条例~ともに生きる社会を目指して~」では、どんな障害があっても、本人が望む暮らしを実現するといった理念が掲げられており、県は、この調査結果をもとに、一層、社会資源の充実などに取り組んでいくことが必要である。そのためには、今回の調査で把握した内容をしっかりと分析し、どのように対応するのか、一人ひとりの障がい当事者の立場に立って、検討していくことが重要である。
そこで、県は、今回の調査結果を踏まえ、障害者支援施設や障害者グループホームの利用を希望する方々にどのように対応していくのか、所見を伺う。
(知事答弁)
次に、障害者支援施設や障害者グループホームの待機者についてです。県では昨年度、施設等の利用を希望する方が障害者本人なのか、家族や関係機関なのかを明らかにするとともに、障害の状態など一人ひとりの実態を把握し、対応を検討するための調査を実施しました。現時点の集計では、175人の方が施設入所を希望していますが、そのうち障害者本人の希望は23人に留まり、多くは家族や関係機関の希望となっています。また、家族等が入所を希望する理由は、介護負担を軽減させたいということが最も多く、入居できるグループホームが少ない、居宅介護といったサービスが不足しているということもあげられています。今後は、入所を希望する障害者や家族の実情を一人ひとり丁寧に把握し、緊急性が高いかなど、個別に確認を進める必要があります。また、地域でのグループホームの確保など、支援体制の充実を進め、家族の負担や将来への不安の解消に向けた取組を進めることも急務です。そこで、県では、7月を目途に、市町村等の関係者に個々の入所希望者の状況を確認するためのヒアリングや追加調査を行うとともに、地域の障害福祉サービスの充実度により、施設入所の希望に差がないかなど、実情をきめ細やかに分析していきます。
その結果をもとに、市町村とともに、グループホームの設置や、地域の相談体制の充実、緊急時の受入先の確保などを進め、本人が望む暮らしの実現と、家族の負担と不安の解消に取り組んでまいります。
(要望)
県は、どんな障害があっても、望む暮らしの実現ができるよう、一人ひとりの障害当事者や、その御家族の状況を丁寧に確認し、相談体制の充実強化をしていくことが求められる。そのほかにも、居住系、訪問系、そういったサービスの充実など、具体的な対応を検討していくことを求める。千葉で起こってしまったあのような事件が、二度と起こらないようにするための取組をお願いする。
(質問要旨)
3 県政の諸課題について
(4) ギャンブル等依存症対策の強化について
ギャンブル等依存症は、誰でもなる可能性があり、また、多重債務や家庭内暴力、犯罪、自殺といった深刻な問題を引き起こすおそれがあることから、社会全体で取り組むべき重要な課題となっています。これに対し、本県では、令和2年度に新たな計画として「神奈川県ギャンブル等依存症対策推進計画」を策定しました。現在は、令和6年度から令和8年度までを計画期間とする改定計画に基づき、様々な取組を進めていると承知しています。こうした中、ここ数年大きな社会問題となっているのが、いわゆるオンラインカジノ賭博です。オンラインカジノ賭博は、違法であるにもかかわらず、その手軽さから20代から30代を中心に広く蔓延し、最近は、芸能人やプロ野球選手が賭博行為を行ったとして書類送検されるなどの報道が相次いでいます。令和6年度に警察庁が発表した報告書では、オンラインカジノ賭博の経験者は、日本国内では、推計で約337万人、年間の賭け額は、公営ギャンブルである競輪に匹敵する約1.2兆円の規模に上るとされており、その対策が急務となっています。この問題に対応するため、今国会では、オンラインカジノ賭博の規制強化と違法性の周知強化などを盛り込んだギャンブル等依存症対策基本法改正案が提出され、本日国会で成立しました。この法案は、カジノサイトの開設・運営を禁止し、SNSなどを通じてこうしたサイトに誘導する行為も禁じる内容で、国と地方公共団体が周知徹底を図るとの規定も盛り込まれております。県としても、こうした法改正の趣旨をしっかりと反映し、取組を一層強化していくべきと考えます。
そこで、知事に伺います。国の法改正を踏まえ、新たな社会問題となっているオンラインカジノを含め、県として、ギャンブル等依存症対策の強化に向けて、どのように取り組んでいくのか、見解を伺います。
(知事答弁)
最後に、ギャンブル等依存症対策の強化についてです。県では、「ギャンブル等依存症対策推進計画」に基づき、県民の皆様が正しい理解のもとで行動いただけるよう、普及啓発に取り組んできました。先月には、国の啓発週間にあわせて、ギャンブル依存は誰でもなる危険性があるという動画を、検索サイトや電車内のビジョンで配信したところです。一方で、いわゆる違法オンラインカジノをはじめとするインターネットギャンブルは、若者を中心に急速に拡大しており、大きな社会問題になっています。実際に検挙された事例では、「違法とは知らなかった」「24時間いつでもできるので、ついハマってしまった」といった声を聞いており、一層の対策が必要です。そこで県では、違法オンラインカジノが犯罪であることについて、ホームページをはじめ、SNSや専用のポスターなどにより、積極的に周知していきます。この中では、今回の法改正で、カジノ賭博そのものだけでなく、そこに誘導するサイトも違法となることなども、分かりやすくお知らせしたいと考えています。また、「分かってはいるが、やめられない」など、本人やご家族が悩みを気軽に相談いただけるよう、「依存症電話相談」をはじめとする様々な相談窓口についても、広くご案内していきます。こうしたことにより、ギャンブル等依存症の対策をしっかりと強化してまいります。私からの答弁は以上です。
(再質問)
法改正を踏まえ、県の「ギャンブル等依存症対策推進計画」についても、これを改定して違法オンラインカジノへの注意をしっかりと盛り込むべきと考えますが、見解を伺います
(再質問への答弁)
「ギャンブル等依存症対策推進計画」の改定についてお尋ねがありました。県の「ギャンブル等依存症対策推進計画」は、昨年度からの改定計画において、違法なオンラインカジノ等が深刻な社会問題となっている状況を踏まえ、すでにこうしたオンラインギャンブルに関する注意を盛り込んでいます。今回の「ギャンブル等依存症対策基本法」の改正については、その趣旨や内容をしっかりと確認し、県の計画のなかにどのように反映していくか検討してまいります。
(要望)
オンラインカジノに対する社会要請を鑑みれば、ギャンブル依存症対策は待ったなしの状況です。法改正の状況を踏まえ、より効果的な取組を実施するとともに、ギャンブルに依存にされている方に対して本当の救済につながる取組を要望します
(質問要旨)
3 県政の諸課題について
(5)県立学校におけるセクシュアル・ハラスメント防止に向けた取組について
令和6年度の県立学校の生徒を対象としたセクハラの実態把握調査の結果で、未だにセクハラで悩み、安心して学校生活を送ることができない生徒が存在することや、教職員からだけではなく生徒間のセクハラが多い実態があることなどが明らかになり、セクハラ被害から生徒を守るための取組が十分ではないと考える。
セクハラの根絶に向け、今回の調査結果をしっかりと分析し、その結果を踏まえ、教職員だけではなく生徒に対しても、さらに効果的な取組を推進することが求められているのではないかと考える。そこで、県教育委員会として、今回のセクハラ実態把握調査結果をどのように受け止め、今後、教職員や生徒に対して、どのような取組を進めていくのか、所見を伺う。
(教育長答弁)
教育関係のご質問にお答えします。
県立学校におけるセクシュアル・ハラスメント防止に向けた取組についてお尋ねがありました。県教育委員会ではこれまでも、人権侵害であるセクハラの防止に向けて、教職員や生徒の理解を深めるため、研修の実施や啓発資料の作成など、様々な取組を行ってきました。こうした中、毎年実施している「県立学校におけるセクハラ実態調査」において、生徒のセクハラ被害がなくならない現状を、深刻に受け止めています。今回の調査では、高齢の教職員によるセクハラ行為が多いことや、生徒間でのセクハラ行為が増加している傾向が明らかになりました。そこで、当事者意識を持たせるため、昨年度にモデル校で実施した、高齢の教職員が自ら講師となり、セクハラ防止研修を行う取組を、すべての県立学校に働きかけていきます。また、生徒がセクハラの加害者にも被害者にもならないよう、調査結果における実例や、相談窓口等を掲載した啓発資料を改めて作成し、セクハラ防止の意識啓発に取り組んでいきます。県教育委員会としては、こうしたことにより、今回の調査結果の分析を踏まえながら、セクハラの根絶にしっかりと取り組んでまいります。
(要望)
学校現場におけるセクハラ被害の根絶に向けて、教職員一人ひとりが、いかに自分事として向き合い、考えていくかが大切だと考えます。今後も様々な工夫を凝らしながら、教職員の人権意識のさらなる向上を図ることを求めます。また、生徒間のセクハラが増加傾向にある中、生徒が、自分の人権も、相手の人権も尊重するという姿勢をしっかり身につけられるよう、人権教育・啓発に努めることを求めます。